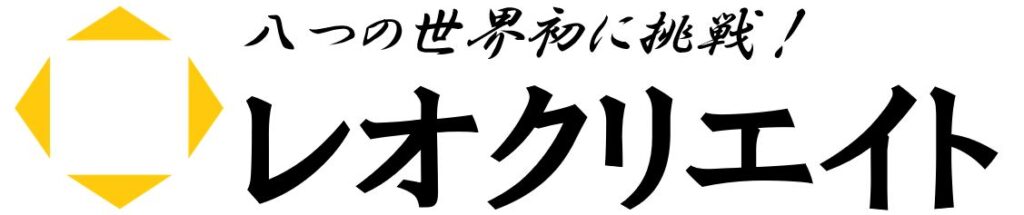- 会津桐を用いた桐製品への活用
硝化処理で得られる撥水効果などの防水性を生かすにはどんな木材が良いかを2022年頃に考えていた時、会津の友人より「会津桐に使ってみれば」とのアドバイスがきっかけで 検討を開始しました。
最初は、喜多方で会津桐の伐採から下駄の生産・全国向けの販売までを行っている「黒澤桐材店」様にお世話になりながら 試作や検証を重ねていき、その後 会津地域の木地師様、木工所様と つながりを増やして 様々な知識を得たり、問題を把握しながら、試作・改善を繰り返し 経験を積んできました。
そこで得た一番の成果は、「桐の食器は実用可能」ということが分かったことです。 写真の右のお椀は新品、左側は 1年半使用したものです。 多少使用感は出ましたが、それは木製品なので当たり前で、撥水性(ここ参照)は十分残り、いまでも普通に使用することが出来ています。
桐製食器の特徴は、日本の樹種の中で 一番の軽さや熱伝導率が低いこと(世界ではバルサに次ぎ二番目)で、とにかく熱いお茶漬け や うどん、味噌汁など、熱くて持てないという不便が解消されます。なにより桐材の木目が光の反射で煌めき美しいので、とても愛着が沸いています。


- 桐以外の樹種の実用性について
他の樹種+硝化処理 の実用性ですが、「木の細胞内部に含浸してガラス微粒子化しているので 性能的には問題ないのだが、ツヤが消える部分がまばらに現れたりして見た目が多少悪くなり、硝化技術の改善 や、使用者様の理解の意識改革 が必要」と考えます。
なぜ 樹種により、硝化処理の性能差が出るか 明確に把握することはこれからの課題ですが、桐は軽量であるがゆえ 木の細胞が大きく細胞壁も薄く、製材によって板状になった桐の板の一面に細胞の穴が存在しているので、硝化処理によるガラスの粒々がその穴に大きく多く入り込み性能を出している、ということが他の木との大きな違いと言えると思います。
樹種としてあまり進化していないと言われる杉などの針葉樹の細胞も 桐に近いものがあり、一面に細胞の穴が存在するので、実用に向けては 次に有望だと考えております。(杉は細胞の穴 全てが導管としての役割を持ち、年輪状の夏目・冬目で細胞の大きさが変化してます。詳しくは別の機会に説明します)
→ 追記:杉は狂いが大きく出て、桐の様には使えない、という失敗実例が出ました。木目は 桐材を上回るほど美しくなることが分かったので、対策を考え、実用になるように頑張りたいと思います。
ケヤキなど 硬くて重い木は 進化の進んだ樹種と言われ、細胞壁が厚く とても小さい穴の細胞部分が多い為、硝化処理を施すと すぐにガラスが詰まってしまうのか ツヤツヤに輝き出すのがとても早いです。 そういう状態で実用的に使用すると、何度も使わないうちにツヤが無くなる部分が現れ、撥水性も低減してきます。 これは細胞の穴が小さい為 ガラス化する量が少ないことが影響しているのではないかと考えております。 しかし 小さい穴ながらも細胞の奥まで含浸して微粒子化しているガラスは存在しているはずであり、ツヤが無くなったから 使い続けることが出来ない ということではなく、現にツヤが無くなって木肌が露出した 硝化処理を施した 斧折れカンバ(斧で切ろうとしても斧が負けるという 硬い木)の箸は、1年間使ってもまだ現役で 問題なく使えてます。(いま磨き直し・再硝化処理のメンテ中。新品同様になりそうです)
以上、今後電子顕微鏡写真など準備して、別の機会に詳細説明したいと考えております。
- 桐食器(上記写真の物)の食洗器 可否
喜多方市内の保育園に桐のお椀を使って頂き、食洗器で半年間洗浄した結果は、変形や撥水性能低下など 大きな問題は出ませんでした。 唯一 ステンレス籠に入れて食洗器での洗浄を行った為、食洗器稼働の振動によって ステンレス針金と桐材との擦り合いによる傷で 口当たりが悪くなってしまったくらいです。 よって気を付けて食洗器洗浄して頂ければ、食洗器の利用は可能と考えます。