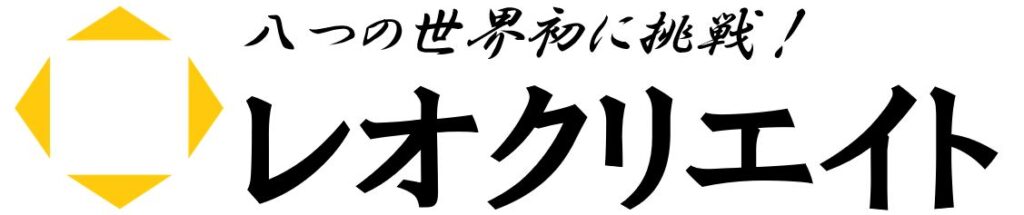アツアツの うどん や トン汁 などの たっぷりの汁ものを食べる時、瀬戸物のどんぶりしか使ったことが無かったため、毎回熱さに耐えたり タオルを挟んで持ったりしてました。 兼ねがね “ 木製どんぶり ” がほしい、と思っていました。
なぜ木製のお椀は沢山存在するのに、木製のどんぶりが少ないのかを木地師の方などに伺うと、通常どんぶりを挽いて製作するには そのどんぶりを作る為の大きな木地(160×160×120 などの大きな木の塊)が必要で、それを何百個、絶えず準備するのが難しいから 作らなくなっていったのでは、とのことで、しかもそれだけ大きな木地の大部分は削りカスになってしまうし、とのことでした。
(木地師の仕事は 長年、同じ形のものを 何百個、何千個 挽いてこそ、1個当たりのコストが下げられる、という仕事をしてきたので、木地が揃わなければ仕事にならない)
このどんぶりは お椀と同じく 会津桐の端材を加工して貼り付けて製作しているので、大きな木地を準備する必要はないし、削りカスもそれほど出ません。 (コストは多少高くついてしまうが…)
写真の左右どんぶりの色が「赤みが強い」ものと「白い」もので 色味が違いますが、硝化処理の方法を変えております。 硝化処理は 木の細胞の奥深くまで浸透してガラス化する為、外の光が細胞の中まで届き、中の細胞が放つ光の反射光の色がもろに出てしまいます。 よって色味の違いで
「赤みが強い」方 → 硝化処理十分で耐久性◎
「白い」方 → 硝化処理が若干弱く、耐久性△~〇
という見た目と耐久性の相関が出てきます。
いまの若い方々からは 圧倒的に「白い」方が良いと 言われますが、耐久性は 赤い方より劣るので、大事に扱えない方には進められない(食べたらすぐ洗って 乾かし、水に漬け置きはしない、など)と説明しております。
「白い」方の使用実績は まだ少なく、これからデータを取り 使用上問題があまり出なければ、白くなる硝化処理を メインの 処理方法にしようと考えています。